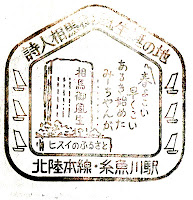ワーグナーを含む数多くのオペラ作品に接するにつれて、私はプッチーニの音楽にも親しみを抱くようになっていた。丁度その時、新国立劇場で歌劇「トスカ」の上演があることを知った。パンフレットには第1幕の聖アンドレア・デッラ・ヴァッレ教会と思われる舞台が掲載されていて、目を見張った。この装置が舞台一面に広がったらどれほど素晴らしいかと思った。それで私は17回目となる結婚記念日に妻をさそってチケットを買い求めた。その席の値段は、他の演目よりも高く、さらに私のこれまでのコンサートでも1,2位を争うほどに高額だった。
歌劇「トスカ」などは、年中いつもどこかで上演されているようだし、いまさら何をという気持ちがしないでもない。私が最初に実演で見たオペラも「トスカ」だったし、そのことは前にも述べた。それでも私はこのオペラのすべてを味わい尽くしているかといえば、それには程遠い。所有する唯一のCDであるモンセラット・カバリエの歌うコリン・デイヴィスの録音だって、何回か聞いた程度にすぎない。
でもやはりオペラは実演に接するに越したことはない、と今回改めて思うのに数分とかからなかった。指揮者の沼尻竜典が棒を振り下ろすと、ピットの東京フィルハーモニー交響楽団は、ほぼ完璧といえるような音楽を奏ではじめた。脇の2階席の最前列で見ていると、オーケストラも良く見えるし、舞台にも近い。幕があいた瞬間、その豪華な教会の内部に見とれたが、光の加減によって様々な場面を形成する。新国立劇場の照明はいつも大変印象的だ。
ライト・モティーフというような音楽用語も、「トスカ」を参考にするとわかりやすい。スカルピアのテーマで幕が開き、トスカのテーマが流れると、これから始まる物語の予感がして感極まる。「歌に生き、恋に生き」のさわりのメロディーが、カヴァラドッシとの愛情のシーンに重なって、うっとりさせる。トスカはここで青い衣装で登場し、一頭映えていた。
少年たちが出てきてテ・デウムの練習をし始めた時に、いよいよスカルピアの登場である。その印象的な部分で照明が一気に明るくなる。そしてしばらくすると舞台が動き、何と教会の内部が広がって大変豪華なシーンとなった。そのすばらしさを見るだけで、この上演を見る価値があるだろう。わずか数分の最終シーンは、音楽がクライマックスになることもあって、前半最大の見所であった。オーケストラも大変上手い。
興奮気味に第1幕がおわり、25分の休憩の後、第2幕となった。この第2幕はスカルピアのオフィスが舞台で、舞台としてはさほどでもないが、奥と左右に扉があって、拷問のシーンは向って左、人が出入りするのは奥、そして窓をあけて外の音楽が聞こえてくるのは右手となっている。一挙手一投足に音楽が付けられての丁々発止のやりとりは、このオペラ最大の見所だろう。CDで聞いていただけではわからないドラマとしての音楽が、ここで十全に示される。ドラマにあわせるように舞台奥からトスカの歌声が重なって聞こえてくるあたりは、プッチーニの音楽の最高のものではないだろうか。
スカルピアは窓から舞台外へ消えて、舞台にトスカだけが残るのは、アリアを歌うための演出である。ノルマ・ファンティーニの素晴らしい歌声は、ここで最高潮に達し、その力強くも宿命的な哀れさを持った声は、マリア・カラスを思い出させる。満場の拍手は一度収まりかけて再び盛り返し、天井桟敷からは多くのブラーバの声が鳴り響いた(前回の上演でのこのシーンの模様が、YouTubeにアップされている)。
トスカが引き立つのはスカルピアが素晴らしいからでもある。韓国のバリトン歌手センヒョン・コーは、小柄ながらも憎い警視総監の役をこなし、同行した妻によれば「これほど憎いものはない」という演技であった。もしかすると小ささゆえのコンプレックスが、スカルピアを悪者にしたのではと思わせるようなところがあった。
再び25分の休憩をはさみ、最終幕は夜空に城壁内部と銅像がそびえ、そうかここがあのサンタンジェロ城の内部かと思いを新たにすると、何と舞台が動いて牢屋が全面に出現し、カヴァラドッシ役のサイモン・オニールは「星も光りぬ」を心をこめて歌った。そのメロディーへと流れていく第3幕の冒頭の音楽は、何と美しいのだろうと思った。そしてそこへトスカがやってくるシーンは、ワーグナー顔負けのドラマチックな抱擁シーンである。プッチーニはおそらく意識して真似たのではないか。
夜が明けようとしている城壁で、射殺刑のシーンになると再び舞台が動いて牢屋が消え、城壁の内部(屋上)へと戻った。トスカは迫り来る兵士の前で後方に飛び降り、舞台は幕となった。
全体にほぼ完璧なオーケストラと指揮、3拍子揃った歌手と豪華で見応えのある舞台装置、照明と衣装の演出(イタリア人のアントネッロ・マダウ=ディアツ)も大変素晴らしく、満席の客からは惜しみない拍手が送られた。カーテンコールは4度、5度と繰り返され、鳴り止まぬ拍手をあとに紅潮した聴衆が雨上がりの寒い街へと消えていった。新国立劇場の「トスカ」は単なる客寄せの芝居ではなく、大変充実した世界的レベルの上演であったと言うべきだろう。だから何度も繰り返され、そして高額のチケットも売れるのだろう。
5回の公演の最終回を見た。マチネが終わるともうすでに真っ暗で、私たちはタクシーで渋谷へと出向いた。新婚旅行で出掛けたポルトガルの料理で舌鼓を打ち、 ワインで程よく酔いかけた頭に、あの甘美なメロディーがしばらく鳴り響いていた。
 そのような素人でも、それだけで完全な交響詩のような第1楽章をきけば、もう十分であるように思う。それぐらいこの楽章は気合十分な曲である。もちろん第1番ほど印象的な主題があるわけではないので、聴き終わってもあまり心に残らない。随分派手な曲だなあ、などと思う。そしてこのデュトワを伴奏としたヤブロンスキーの演奏は、このような曲でも手を抜かずに一定の完成度で聞くことができる。
そのような素人でも、それだけで完全な交響詩のような第1楽章をきけば、もう十分であるように思う。それぐらいこの楽章は気合十分な曲である。もちろん第1番ほど印象的な主題があるわけではないので、聴き終わってもあまり心に残らない。随分派手な曲だなあ、などと思う。そしてこのデュトワを伴奏としたヤブロンスキーの演奏は、このような曲でも手を抜かずに一定の完成度で聞くことができる。